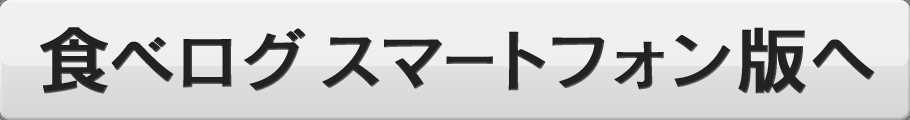その昔、ブルーバックスシリーズの本を、書店で立ち読みしていた時に、
おばあちゃんの知恵的に語られてきたと思われる
「おしるこに塩を入れると甘く感じる」という仕組みについて、
明快に書かれているのを目にしました。
その時、人の感覚の仕組み、そして先人の知恵に、
えらくうなってしまいました。
■ブルーバックスによる、おしるこに塩を入れる理由曖昧な記憶ですが・・・・
本来は甘いはずのおしるこに相反する塩を入れると、
返って甘味を感じる。
それは、まず
塩と砂糖の分子量の違いがある。
・塩 (NaCl) 分子量:約58
・砂糖(C12H22O11) 分子量:約342
分子量は約5倍の差があり、砂糖は巨大なかたまり、塩は小さい分子です。
おしることが,舌の上にのると、最初に、
分子量の小さい塩が先に浸透し、脳に刺激を与える。
しかし、脳はまだ刺激を受け取る準備ができていないため、
塩の味に対する反応が鈍い状態。
そのため、
塩の味をあまり感じないらしい。
ところが、一度、
感覚に刺激が与えられると、スタンバイ状態となり、
次にくる甘味に即座に反応できるため甘く感じる。
そんなようなことが書かれていたと記憶しています。
これは、昔、映画館など真っ暗なところにいきなり入ると、
目が見えなくなってしまうので、
片目だけ手で覆っておくと、暗さになれるので、
いきなり暗闇に入っても、見えなくなることはない。
そんなことを、聞いたことがありましたが、
それと同じ原理ではないかと、その時に思っていました。
■昔の人は、すごかった・・・おばあちゃんの知恵のように伝えられてきたと思っていた
おしるこに塩、あるいはスイカに塩・・・・・
その裏にはは、
分子量という物質の性質による浸透の差があり、
さらに、
神経の伝達と刺激への人の反応の仕組みが存在していた
ということに、とても驚きました。
おそらくそんな理論なんて知らずに、
経験的に伝えられてきたことだと思うのですが、
先人の知恵の素晴らしさみたいなことに、えらく感心しました。
■お料理のコツには科学があるそこで、お料理のコツと言われてきたものの裏には、
昔はわからず経験的にしていた事の中に、
きっと、このような科学が存在しているんだ・・・・
そのことに、おもしろさを感じたのでした。
この情報を知って以来、甘味をより感じるため、塩を使うという原理は、
こういう理由だと、ずっと思っていました。
■コツも社会の変化によって変化そしてこれらの背景には、昔は貴重だった砂糖を、
より甘く感じさせるための知恵だったのかも・・・・
そんな社会的な背景があったのかもしれない。とか、
最近は、スイカに塩をかける人があまりいなくなっている気がします。
(というより、スイカを食べる機会も少なくなっているような気も・・・・)
昔はそんなに食べるものも豊富ではなかったので、
夏といえばまるごとのスイカがどこの家庭にも冷蔵庫に入っていました。
きっと、当時のスイカはそんなに甘くはなくて、
塩をふって甘味を感じさせていたのかもしれません。
次第に、品種改良などもすすみ、甘味が出てきたため、
塩をふらなくてもよくなってきたとか・・・・・
あるいは塩分、摂取を控える傾向が出てきて、かけなくなったとか・・・・
社会の変化に伴い、習慣も変わっていくのかも・・・・
なんてことを思いながら、久しぶりに広げた『コツの科学』を見ると・・・
■「コツの科学」による塩を入れると甘いという原理は?おしるこやスイカに塩を入れるのはなぜか という記載がありました。
ここに書かれていたことは、私がブルーバックス見た理由と
ちょっとニュアンスが違っていて、
「対比効果」で説明がされていました。
おしるこの塩は、甘味が強くなる効果の他に、
味全体が引き締まる効果も。
対比効果のポイントは、一方の味が十分に強く、他方がごくわずかであること。
塩には対比効果を起こしやすい性質があると書かれていました。
神経系の話には触れていませんでした。
この対比という概念は、現象をとらえているだけで、
どうして、そういうことがおきているのか・・・
という根本のことは、この説明ではわからないと思ってしまいました。
食物学からとらえる「塩」と、神経系の生理学なども含めて捉えた「塩」
原理の捉え方が違う・・・と感じたのでした。
同じ塩の効果も、化学畑の方と、食品関係の方と、
体の仕組みも知った上で、理解しようとする人とで、
理解のしかたの違いがあるような気がしてきました。
■実験による塩の効果コツの科学では、実験データが示されていました。
砂糖20%の味に対して、食塩の添加量(0~1.5% 0.2刻み)によって、
甘味の感じ方の順位が示されていました。
一番、甘味を感じられたのは、0.5%の食塩でした。
(何人ぐらいの人で実験したんだろう・・・とか
人によって甘味の感じ方、違うと思うけど、
そなあたりは、どう処理して結果を出したのかな? とか・・・
またまた、なぜなぜ、スパイラルに入ってしまいます 笑)
■ネット内で、甘味に塩を加えることについては・・・今、ネット内では、この塩について、どう語られているのでしょうか?
やはり
「対比効果」で説明されているのが主流のようです。
神経の伝達との関係の話は、私が見た限りではありませんでした。
おそらく、これらの元ネタは、下記ではないかと思うのですが・・・
たばこ塩産業 塩事業版 1998.5.25
塩なんでもQ&A
(財)ソルト・サイエンス研究財団専務理事 橋本壽夫
⇒
塩の対比効果と抑制効果 ◆
おしるこに塩ひとつまみ。甘みが増す2つの理由。 上記に次のような記載がありました。
ーーーーーーーーーーーーー
おしるこに塩をひとつまみ入れると甘みが増します。
この甘み増強効果には、大きく二つの理由があります。
一つ目の理由は
「対比」といわれる、
「対比」のメカニズムはまだよくわかっていない部分も多いのですが、
実験では
舌ではなく脳のレベルで起こっている可能性が高いことが示唆されています。
二つ目の理由は、
脳だけでなく
受容体のレベルでも増強効果が生じているということです。
舌には味蕾があり、その中の味を感じる細胞には甘味受容体があります。
甘味受容体には砂糖などの分子が入るポケットがあります、
砂糖を甘く感じるのは、砂糖分子がこのポケットに入るからです。
食塩は受容体の形を若干変えます。
その結果、砂糖分子はポケットに入りやすくなり、
甘みを強く感じるようになるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
以上のように、「対比効果」が、体のどこで、どのようにおきているのか・・・・
ということまでを知りたいと思ってしまうのでした。
■味覚カウンセラー???ところで、またまた新たな資格?「味覚カウンセラー」
そして、味覚カウンセラー協会なる組織。
味という世界には、いろいろな団体が立ち上がっているようです。
このあたりを探ってみると、またおもしろそうです。
=============
【参考】以下は、あとからもう少しよく見たいと思ったサイト。
あとで探すとみつからなくなるのでここにストックしておくことに・・・
今も、一つ、サイトがみつからない・・・・
○
料理を美味しくする塩 ○
「料理人なら知っておくべき“塩味”のコト 第1回(全4回)」 ○
似て非なる砂糖と塩の不思議 ○
なぜ、調味料の順番は「さしすせそ」なのか。 そもそもの疑問は、自然塩と、精製塩の分子構造は同じなのか・・・
という疑問からスタートした塩の話。
タイムリーに塩の講座もあったため、その記録も兼ねたので、
ちょっとのつもりが、すごい大回りになってしまいました。
さらに、「おいしい」ということは、どういうことなのか・・・
そこには、味覚の感じ方の生理的なことも関係しているようです。
そこまで広げると収集がつかなくなりそうなので、
またの機会にすることに・・・・・
ということで、塩の話は、一旦、ここでお開きにすることにします(笑)