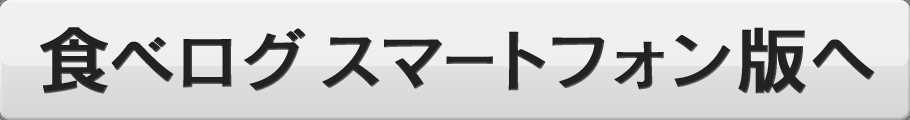神様に格付けなどあるわけない。あれば、一番高い神様ばかり拝むようになってしまう。ご利益にまで差が出てしまうのだ。
しかし、神社には格付けらしきものがある。誰が作ったとも選定したわけでもない。確かに1946年までは神社が国家管理されており、近代社格制度というものが存在していたが廃止された。以降、伊勢神宮を除くすべての神社は対等の立場とされている。
ただ、別表神社というものがあるこれは神社の格付ではなくて神職の進退等に関するもの。これは神社本庁が定めた、神社本庁が包括している一部の神社のことである。まあ、神職の人事にかかわるものだろう。
伊勢神宮(正式名称神宮)は、明治政府によって天皇家の先祖を祭った神社となった。そこで、国家神道の名の下に全国の神社を系列化に置いた。全国の神社の総本山としての機能を持ったのだ。しかし、1945年の終戦で。政教分離政策がGHQ命令で行なわれた。
全ての神社に対する国からの援助・神宮による支配が無くなり、各神社は個別の宗教法人になった。これに対し伊勢神宮側は神社庁を設立し、神主の資格を管理している。ただし鎌倉宮、靖国神社、日光東照宮、伏見稲荷大社、明治神宮は、神社庁から脱退している。
出雲大社(正式名称大社)は、明治になり出雲大社と名乗る事を命令された。日本書紀に「天皇家と対立した勢力」となっているので、(伊勢)神宮に対して大社と名乗る事にしたらしい。今は、出雲大社教本山として独立している。
他方、まったく別の見方もある。宮司の家系である。不敬かもしれないが。歴史の通説であるので仕方ない。天皇家の家系は神武天皇以来何度も途切れている。南朝・北朝しかり。ところが、一度も途切れていない家系が⒉家あるのだ。
島根の日御碕神社の宮司の家系で小野という家。なんとスサノオノミコト(素戔嗚尊)の子孫である(99代目)。出雲に実在している。また出雲退社の千家という家系も84代途切れなく、正真正銘の直系である。私はこの方に会った事がある。仏様(いや神主様)のような顔をされていた。
従って、神社の格を云々する時に、この家系を重要視する人もいるのである。そういう方々は、出雲大社を伊勢神宮より上に置くようだ。
因みに、ある方の格付を付記しておく。あくまで参考だが。
1.伊勢神宮 説明不要、別格の神社。
2.出雲大社 これまた別格の神社。近代社格制度下において唯一の大社。
(明神大社・出雲国一宮・官幣大社・勅祭社・別表神社)
3.賀茂別雷神社(上加茂神社) 官幣大社筆頭。日本三大勅祭のひとつ。
(明神大社・山城国一宮・上七社・勅祭社・官幣大社・四方拝・別表神社)
4.賀茂御祖神社(下鴨神社) 日本三大勅祭のひとつ。
(明神大社・山城国一宮・上七社・勅祭社・官幣大社・四方拝・別表神社)
5.宇佐神宮 八幡宮の総本社。日本三大八幡宮のひとつ。
(明神大社・豊前国一宮・勅祭社・官幣大社・別表神社)
6.石清水八幡宮 日本三大八幡宮のひとつ。日本三大勅祭のひとつ。
(上七社・官幣大社・四方拝・別表神社)
7.熱田神宮 三種の神器・草薙の剣をご神体とされています。
(明神大社・官幣大社・四方拝・別表神社)
8.伏見稲荷大社 稲荷神社の総本宮。
(明神大社・上七社・官幣大社)
9.春日大社 春日神社の総本社。日本三大勅祭のひとつ。
(明神大社・上七社・官幣大社・勅祭社・別表神社)
10位はちょっと決めかねる。以下からお好きなものをどうぞ。
松尾大社・住吉大社・日吉大社・八坂神社・諏訪大社・富士山本宮浅間大社・日前神宮・國懸神宮・氷川神社・鹿島神宮・香取神宮