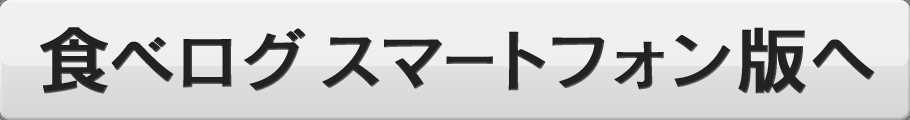東洋経済オンライン 7月1日(金)6時0分配信
■ 空前の「糖質制限ダイエット」ブーム
糖質制限ダイエットが、空前のブームを迎えている。厚揚げをパンに見立てたサンドイッチ、肉と野菜だけが詰まったお弁当、こんにゃく麺を使った冷やし中華――。人気画像投稿SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のインスタグラムでも、糖質制限は30万件近い投稿があり、人気の話題だ。
この記事の写真を見る
糖質制限市場を狙ったビジネスも今が花盛りだ。関連書籍や雑誌は今や数え切れないほど出版され、今年に入ってからはコンビニのローソンや外食チェーンのガストなどが、次々「低糖質」を売りにした商品を強化しはじめた。
週刊東洋経済7月2日号(6月27日発売)は、『健康格差』を特集。糖質制限ダイエットの真実にも迫っている。糖質制限とは、血糖値を上げる糖質を多く含んだ炭水化物や甘いものなどを控える食事法のこと。われわれ日本人は、1日の摂取カロリーの6割程度を糖質(成人男性で糖質345g程度=ご飯お茶碗6.2杯分)から摂取しているのが普通だ。そこから、「減らせば減らした分だけ体重が落ちる」(北里大学北里研究所病院の山田悟医師)。 現在は、3食主食抜きの厳しい方法や、夜だけ主食を抜く方法、さらには1食につきお茶碗半分程度の白米を目安とする、ゆるやかな方法などが一般的だ。日本では、糖尿病患者に対する血糖コントロール法として研究が重ねられてきたが、健常者のダイエットにも効果的だと、10年ほど前から徐々に人気が上昇。今や、多少なりとも体型を気にする人ならば、かなりの割合で挑戦したことがあるダイエット方法となった。
.
このダイエットの最大の魅力は、短期間で大きな減量効果があること。Nさん(30代・男性)も、その効果を実感した1人だ。子どもの頃から自らの肥満体にコンプレックスを抱いてきたKさんは、これまでカロリー制限、ジム通いといった数々のダイエットに挑戦しては挫折してきた。藁にもすがる思いで雑誌に特集されていた糖質制限に挑戦してみたのが2年半前のこと。1日3食すべて主食を抜くという厳しいやり方で臨んだところ、身長170cmで76kgあった体重が、半年で15kg落ちた。
今なお、挫折はしていない。「食べることが大好きな僕にとって、お腹いっぱい食べられないのはストレス。その点、糖質さえ控えれば、肉も脂っこいものも食べて良いこのダイエットは自分に合っていた。職場の飲み会に参加しても、乾杯のビールを糖質の含まないハイボールに替えれば良いだけだから、心置きなく楽しめる」(Kさん)。
■ 糖質制限ダイエットのカギ
そもそも糖質を制限すると、なぜ痩せるのだろうか。カギとなるのは、別名「肥満ホルモン」とも呼ばれるインスリンの働きだ。
糖質を摂取して血糖値が上がると、それを下げるために膵臓からインスリンが分泌され、血中のブドウ糖を筋肉細胞に蓄積しようとする。だが、ブドウ糖の量が過剰だと、脂肪細胞がそれを取り込み、中性脂肪に変えてしまう。これが、糖質の過剰摂取が肥満につながる理由だ。白米は茶碗一膳で55g、うどん1玉52gと、われわれが「主食」とする穀物の糖質は高い。
一方、タンパク質や脂質は血糖値を上げない。たとえば脂身たっぷりのサーロインステーキを100g食べたとしても、含まれる糖質はたったの0.3g。血糖値がほとんど上がらず、インスリンの大量分泌も起きないので、太りにくいというワケだ。
糖質制限が、脂質を控えたカロリー制限よりも高い減量効果を持つことは、医学的なエビデンスがすでに複数ある。2008年に世界的な権威を持つ医学雑誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』に掲載された、肥満のイスラエル人に対する2年間の検証によれば、脂質を控えてカロリー制限をしたグループよりも、カロリー制限なしで炭水化物を控えたグループのほうが体重の減少幅は大きく、同時に血中のコレステロール値も低かった。今年6月の米国糖尿病学会では、順天堂大学の研究グループが日本人にも同様の効果があることを報告している。
これだけを聞けば、史上最強のダイエット法のようにも思える。だが、従来の食事の栄養バランスをガラリと変えることになるため、気になるのが安全性だ。「頭がぼーっとする」「階段で息が上がる」というちょっとした体の不調から、「あの著名人の死は糖質制限が原因ではないか?」という深刻なものまで、さまざまなレベルでのうわさが飛び交う。そして事実、日本糖尿病学会が2013年に出した提言では、長期間にわたって極端に糖質だけを制限した食事は「推奨しない」としている。
ただし、数々の「糖質制限危険論」のなかには、間違った糖質制限が原因で引き起こされる不調を指摘している場合や、科学的な根拠が薄いものも少なくない。
まず、「頭が働かない」「力が出ない」といった不調は、糖質制限のやり方を間違えていることが原因だ。糖質制限の第一人者として知られる高雄病院の江部康二医師は、こうした症状について「9割9分の確率でエネルギー不足を起こしている」と指摘する。
熱心なダイエッターたちはつい、脂身たっぷり肉などに抵抗を感じ、低カロリーの豆腐や鶏のささみ、野菜ばかりを選びがちになっている。すると、体重や脂肪は急激に落ちるが、同時にエネルギー不足で元気もなくなってしまう。江部医師は、「適切に行う秘訣は、炭水化物を控えて不足する食物繊維やビタミンCを葉野菜などから補ったうえで、適正カロリー内で動物性脂肪やタンパク質をしっかり取ることだ」と指摘する。
死亡リスクについては、2008年に聖路加国際病院の医師らが、「5年以上の糖質制限で死亡率が高まる可能性がある」という結論の論文を発表。糖質制限危険論者の筆頭格、日本糖尿病学会もこれを論拠の1つとしている。
■ 論文に問題点あり
だが、この論文に問題点が多いことは、すでに複数の専門家が指摘していることだ。山田医師は、この論文が「因果関係のわからない『観察研究』という手法によって書かれているため、死亡率上昇の原因が糖質制限にあるとは言えない」と言う。江部医師によれば、「信ぴょう性のまちまちな論文からデータを集積して記されているため、全体の信ぴょう性が低くなっている」。
この論文は欧米人を対象にしたものだが、2014年に出た日本人を対象とした同様の研究では、糖質摂取量の一番低い被験者の死亡率が最も低い、という正反対の結果も出ている。
糖質制限の危険性を明確に裏付ける根拠が出てこない状況を受けて、長らく糖質制限に異端のレッテルを貼っていた米国糖尿病学会が変わり始めた。まず、2008年には1年間の安全保証期限付きで糖質制限の有効性を認め、2013年には期限なしの容認に至ったのだ。
そして、いまだ糖質制限への慎重な姿勢を崩していない日本糖尿病学会の中にも変化の動きが出てきた。6月中旬に糖尿病学会理事長で東大教授の門脇孝医師にインタビューしたところ、「(糖尿病学会の理事長ではなく)一人の糖尿病研究者として、糖質量を総摂取カロリーの4割以下に抑える糖質制限は、大いに推奨される」との見解が示されたのだ。
門脇医師が推奨するのは、平均的な体格の男性で1日の糖質量を150g以下(=白米茶碗2.7膳分)のゆるやかな糖質制限。実際、東大病院では2015年4月から、糖尿病患者の食事として、従来の糖質が1日の総摂取カロリーの5割以上を占めるメニューに加えて、この4割の「低糖質」メニューも用意しているという。
門脇医師は、実は自身も糖質制限の実践者。「安全性への検証が進めば、より自信をもっておすすめできるようになる」とも言及。かつては糖質制限を強固に反対していた学会内において、そのトップが糖質制限を容認したことは大きな意味を持つ。
■ 安全、危険と言い切るにはまだ早い
間違えてはいけないのが、糖質制限を危険だとする根拠がない一方で、同時に糖質制限を20年、30年といった長期で行った場合に本当に安全なのか、それを証明する検証結果もまた無いということだ。さらに、深刻な腎障害を持った人や妊婦など、糖質制限には慎重になるべき人がいる。
ひとえに糖質制限と言っても、すべての人に同じやり方が適当なわけではないことも忘れてはならない。東京イセアクリニック特別顧問の久保明医師は、現在の糖質制限の加熱ぶりに対してこう警告する。「糖質制限を始めるにあたって、今の自分がどのような健康状態で、普段どのような栄養素をどの程度取っているのかという視点が欠如している人が多すぎる」
糖質制限は危険か安全か、という単純な2元論ではなく、そもそも自分の嗜好やライフスタイルに合った方法なのか、そして自分の目指す体型になるために、現在の食事の何をどう変えれば良いのか。そこから考えるのが最短ルートといえよう。
.
印南 志帆